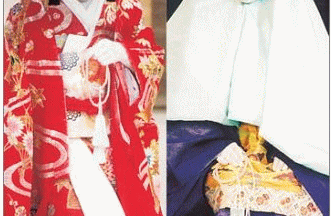※当ページのリンクには広告が含まれています。
獅子物の古典である「枕獅子」をもとにつくられたのが「鏡獅子」。
九代目市川団十郎が初演の新歌舞伎十八番のひとつですが、六代目尾上菊五郎の名演によって不動の地位を確立しました。
【あらすじ】
白いたてがみ、きりっと、見開いたまなこの獅子の精は、日本画、日本人形でもおなじみの題材。
前半は、将軍さまお気にいりの初々しい女小姓「弥生」。
後半は、勇壮で力強い獅子の精。
ガラッと変わる二役を、一人の踊り手が描き分ける大曲。
華麗なる変身の「美学」といえるでしょう。
お正月の将軍家のお城。初釜のお手前をしていた、女小姓の弥生が、座興におどりをお目にかけるよう、大広間に呼び出されます。
ふくさをもったまま登場する弥生。
深々と一礼し(客席を将軍の座に見立てて)、田植え唄、おぼろ月夜にホトトギスが飛ぶ情景、紅白のぼたんが咲き誇る様子など、身ぶり、手ぶり、扇を用いて、一心に踊りこんでいきます。
踊りおさめに、神棚にまつってある手獅子を持って舞う弥生。
その獅子の精霊が、弥生にとりついたように、動きの自由を奪い、弥生をどこかへ連れさってしまいます。
飛びかう二羽の蝶とともに、ふたたび姿を現したとき、弥生は白いたてがみの獅子と一体化しています。
神々しい雰囲気のうちに幕が下りる。